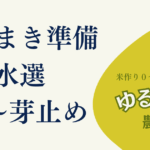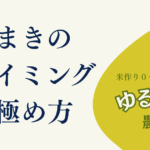地域差もありますが、新潟・下越地域では稲の種まきの準備が始まってきました!
今回はその工程を確認していこうと思います。
再確認や新しい発見の助けになれれば幸いです。
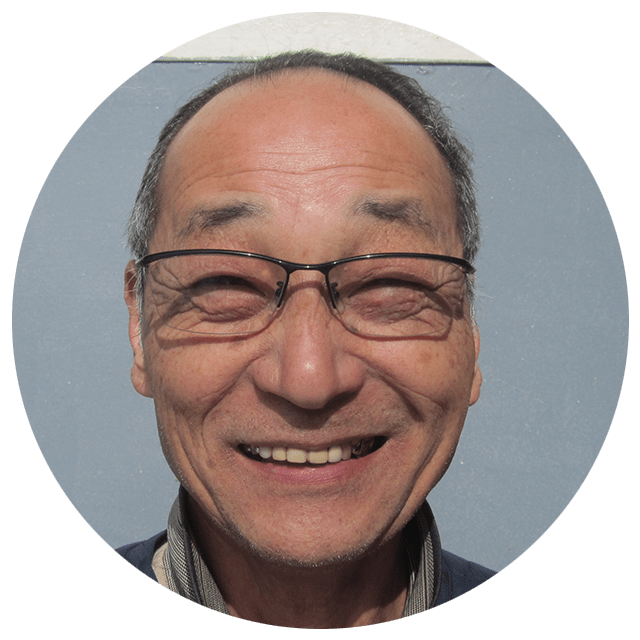
百津屋商店 代表:和田 一男
教科書に載っていないようなコツでサポートいたします!
お気軽にお問い合わせください!!
まずは種籾の選種
まず最初にやってほしいことは「塩水選(えんすいせん)」ですね。
購入種子、自家採取を問わずやった方が良いです。
罹病種子を取り除き、より充実した種籾を選ぶことで素質の良い充実した苗になり、生育も揃います。
発芽して自立するまでは種籾のデンプンを使いますので、ポテンシャルの高い種を揃えた方がその後の生育がスムーズにいくわけです。
塩水選後は徹底的に水洗いと水切りをしましょう。
その次に行うのが消毒
この時点で種籾を袋に入れるわけですが、あまりギュウギュウに詰めずに余裕をもって入れてください。

温湯消毒と薬剤消毒の2通りのやり方があります。
薬剤消毒ではお使いの薬剤の倍率・消毒時間を確認して行ってください。
消毒後の水洗い・乾燥は不要です。
続いては「浸種(しんしゅ)」

「浸種」とは種籾が発芽するのに必要な水分を吸収させることです。種籾も人間のように水を飲むのが速いものとゆっくりなものがありますので、10~13℃くらいの低温で10日ほどじっくり吸水させます。水温は低すぎても高すぎても良いことはありません。
浸種を初めて最初の3日間は消毒効果を高めるためにそのままにしておき、その後は2日おきに水の更新を行います。
百津屋では浸種の最後の2日間(48時間)に「ネバルくん」を投入してもらうことをおススメしています。

手間をかけず、ただ投入するだけで名前の通り、「根張りがバツグンに良くなる」とお客様に喜ばれています。
崩れる心配のないマット状の根張りを簡単に手に入れませんか?
今度は「催芽(さいが)」に移ります。
健苗つくりのカギは、太い芽をそろえて出すことです。
催芽温度は30~32℃とし、芽が1㎜ほど出芽した状態にします。
品種によって発芽までの時間が違ってくると思いますが、芽が出るころになるとモミが透き通って見えてきます。タイミングを見逃さないように注意しましょう。
種籾の準備最終工程は芽止め
90%以上が出芽したのを確認できたら「芽止め(めどめ)」をします。
余熱で芽が伸びすぎないように種籾の温度が13℃以下になるまで冷水で良く冷やします。
その後に広げて乾燥させますが、乾きすぎて「胴割れ」をさせないように陰干しを行いましょう。扇風機などで風を送ると時短になります。
数種類の品種をまとめて管理している場合は、それぞれの品種がしっかり確認できるように注意してください。(タグなどが風で飛んでしまってわからなくなった。なんてこともしばしば聞いております。)
乾いたモミを袋に戻したら、種まきまでの準備は一旦終了となります。
米つくりの最初の一歩、しっかりとした準備で気持ちよくスタートしましょう。
ネバルくんはAmazonでも手軽にご購入可能です。
参考:
1Kg https://amzn.to/3Oz7zwE
100g https://amzn.to/3SPI6Sn
関連記事
初心者の方向けシリーズ「ゆるっと農業入門|知識ゼロ歓迎の農業予備校」でもご紹介しております。併せてご覧ください。
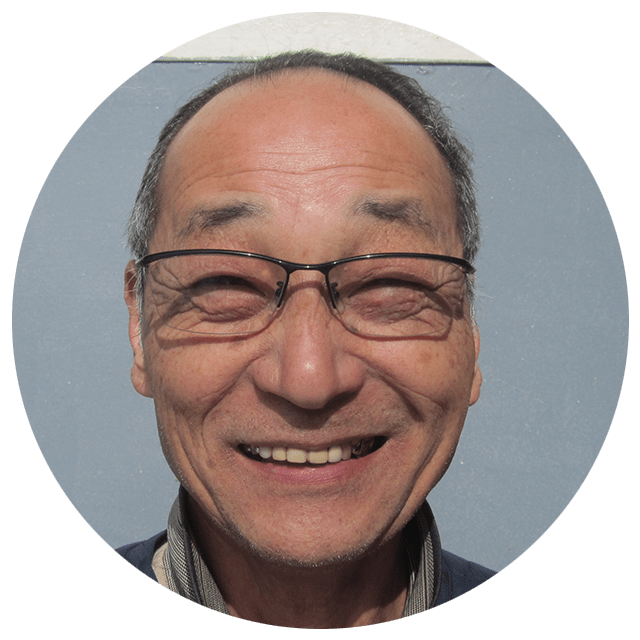
百津屋商店 代表:和田 一男
教科書に載っていないようなコツでサポートいたします!
お気軽にお問い合わせください!!