新潟県下越地域ではコシヒカリで1㎜の幼穂が確認できました。(2019-07-09現在)
この圃場では肥切れの兆候が出ていたため、幼穂形成が早まったのだと考えられます。
現在を出穂25日前だとすれば、8月3日の出穂と予想できます。
コシヒカリは耐倒伏性が非常に弱い品種です。
加えて今年の長期予報によりますと、「全国的に7~8月にかけて曇りや雨の日が多い」と発表されています。
穂肥のタイミングは慎重に検討していきましょう。
目次
穂肥の目的は?
適度な栄養を与えることによって穂の数、籾の数を確保して、ついた籾をしっかりと充実(登熟)させることによって収量と品質の向上を目指すために穂肥を施用します。
穂肥の施用タイミングは?
穂肥の施用を決めるには”幼穂の長さ”を確認するところから始まります。
圃場の中の平均的な出来の株から主茎(親茎)を抜き取り、
- カッターで切り込みを入れて確認 するか
- 手で葉を剝いて確認します。複数の株で実施することで精度が上がります。
(1)

(2)

上の図を利用していただければおおよそ出穂何日前なのかの判断ができると思います。
次に
- 節間の長さ
- 草丈
- 茎数
- 葉色 などなど
を確認しながら穂肥を施用する回数、時期、量を決定していきます。
穂肥を2回施用するのが一番多いパターンかと思いますが、理想は稲の状態を見極めながら短い間隔(3~5日)で細かく施用してあげることです。
チッソを入れられない状態でも、リン酸やカリ、ケイ酸を施用することで稲体は活力を得られます。
実りの秋に向けて
収量と品質を確保するためには、上位5枚の葉と根を最後まで生かしておかなくてはいけません。
- 止葉 : 穂へのデンプン供給
- 中位葉 : 稈へのデンプン供給
- 下葉 : 根へのデンプン供給
- 根 : 肥料分を止葉に供給
というふうにそれぞれが重要な役割を持った分業体制をとっています。
それぞれが十分な力を発揮してこそ、粒張りの良い倒伏しない稲体が出来上がるのです。
適切な施肥管理と水管理(間断かん水)で実りの秋を迎えましょう!
参考ページ
あわせて読みたい

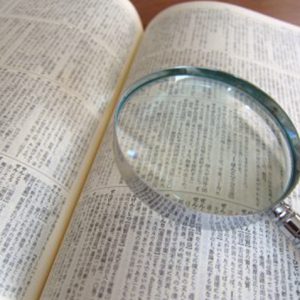
「穂肥(ほごえ・ほひ)」の意味
穂肥とは 「穂肥」とは、穂の籾を充実させることを目的とした肥料を言います。 作物の生育後半、特に穂が出る前後に施す追肥のことを指します。この時期に施す肥料は、...

