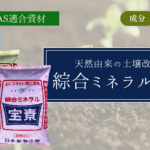良食味・多収穫を目指す土つくり「秋起こし」
「秋起こし」とは
ご存知のかたも大勢いらっしゃるかと思いますが、改めて説明しますと「秋起こし」とは稲刈り後の田んぼを文字通りに秋のうちに耕運することです。
地域によってはあえて行わないところもあるようですが、百津屋としてはこの時期の土作りが来年の高品質化や収穫に大きく関係するだけではなく、しっかりと行うことで代かきなどの作業も楽になることから秋起こしを推奨しています。
「秋起こし」の目的


秋起こしは秋のうちに耕運をすることで有機物の腐熟を促進し、下記のようなリスクを軽減して春先の作業の効率・効果を向上させることができます。
- 窒素飢餓
- ガス害(ワキ)
稲刈りの時にコンバインから排出される細かくなった稲わらですが、翌年の春までそのままの状態で放置していてもなかなか腐熟は進みません。
未完熟の稲わらは代かきの時に浮かんできたり、微生物が分解するときに窒素を急激に消費することで起こる”窒素飢餓”状態におちいる危険性があります。また、田植後くらいに発生するガス害(ワキ)の原因になります。
また微生物の動きが活性化することで団粒構造化が進むことで通気性、通水性、保水性が増し、さらに微生物の動きが活性化するという良いスパイラルが生まれることになります。
次に「秋起こし」タイミングとやり方をご説明します。
稲刈り後はできるだけ早く「秋起こし」をしよう

当サイトでも何度か説明しておりますが、
有機物の分解をする主役は「微生物」です。
低温のなかでは微生物の活動が非常に鈍ります。
ですのでなるべく早く平均気温が15℃以上あるうち、天気が良くほ場が乾いた時に作業を始めましょう。
耕運の深さはそれほど必要なく、有機物が土の中に混ざるようにすれば大丈夫です。


秋起こしの際、稲わらの他に「モミガラ」をすき込むことで、土壌の物理的な改良と、ケイ酸などの補給という科学的な改良が期待できます。
「綜合ミネラル宝素」で地力を上乗せ
上記のような有機物に加え、「綜合ミネラル宝素」を投入することでさらに「地力」が向上します。
チッソ肥料などは早めに施肥してしまうと流亡してしまいますが、「綜合ミネラル宝素」はケイ酸を主体とした天然微量要素肥料ですのでいつでも施肥することができます。
また、[粒状]ミネラル宝素の場合、造粒の際に使われる”糖蜜”が微生物のエサとなり、より一層活動を活性化させます。
もうすでに土の中は来年に向けて動き出しています。今からできる土作りで最大限の効果を引き出しましょう!